
更新 住宅の知識

狭い土地でも広い住まいをリーズナブルに実現できるのが、木造3階建て住宅。都市部を中心に人気が高まっていますが、一方で「火災や地震に弱いのでは?」といった声も少なくありません。
せっかくのマイホームですから、安全性もコスパも妥協したくないですよね。家づくりの満足度を高めるには、メリットだけでなく、リスクや注意点もきちんと理解しておくことが大切です。
本稿では、鉄骨造との違いを踏まえ、木造3階建て住宅のデメリットや注意点を解説します。また、それを補って余りあるメリットもご紹介しますので、家づくりの判断材料にご活用ください。
| 目次 |
|---|
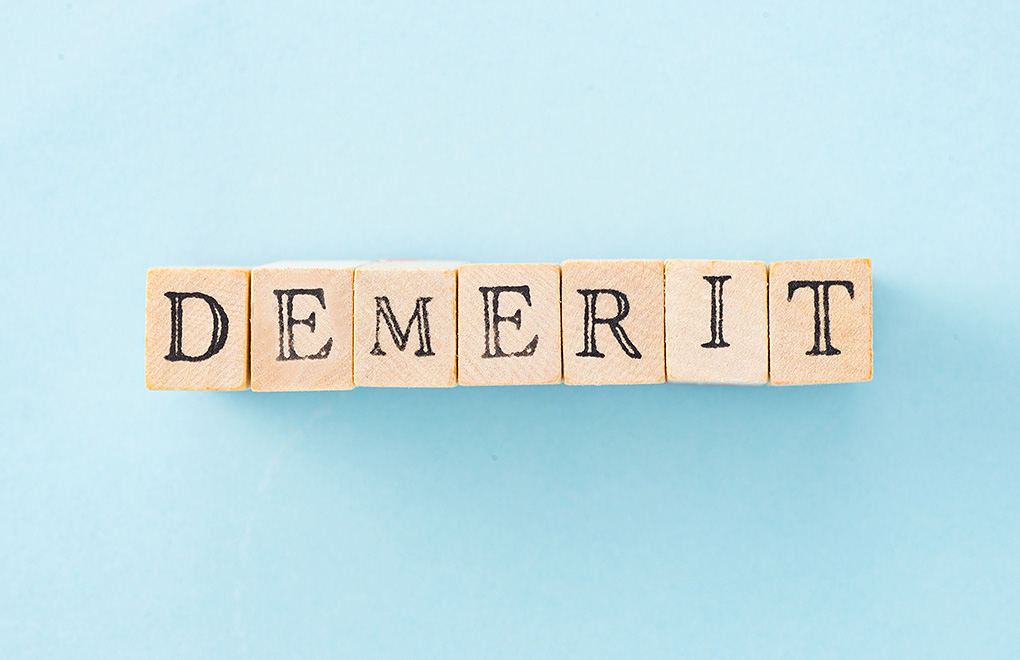
木造3階建て住宅は、土地の有効活用やコスト面の魅力から人気があります。一方で、構造や法規面で特有のリスクや制約もあります。
ここでは、とくに注意しておきたいポイントを取り上げます。知っておくことで、設計や施工の段階で適切な対策が取れ、長く安心して暮らせる家づくりにつながります。
▸鉄骨造に比べて火に弱い
▸鉄骨造に比べて構造の安定性を確保しにくい側面がある
順番に、詳しく解説していきましょう。
木造住宅は、鉄骨造に比べて火災に弱いというイメージがあります。
実際そのとおりで、かつては「防火地域」や「準防火地域」と呼ばれるエリアでは木造3階建ての建築は認められていませんでした。
しかし、建築技術や建材の性能が向上したことで、1987年の建築基準法改正以降は一定の防火性能を備えた木造3階建ても建築可能になっています。
つまり、法律で定められた対策を施せば、ある程度の時間なら火災に耐えられる木造3階建てを実現できます。
参考:東京理科大学「もう少し知りたい防火の基礎知識 木造3階建て戸建て住宅の解禁」
木材は高温にさらされると燃えます。ただし、表面が燃えて炭化すると内部への熱の伝わりが遅くなり、燃え進みにくくなる特性があります。
そのため、太い木材を使うと倒壊までに一定の時間を稼ぐことができます。このような特性を生かし、表面の燃焼を考慮して木材の厚みを決める手法を「燃えしろ設計」と呼んでいます。
一方、鉄骨は不燃材料です。ただし、高温で軟化する性質を持っています。そのため鉄骨造も、火災時に変形して建物の倒壊につながる危険性がないとは言えません。
たとえば400℃で約2/3まで強度が低下し、1000℃を超えると強度はほぼ期待できなくなります。
木造3階建てを「防火地域」や「準防火地域」に建てる場合、消防法や建築基準法で耐火性能に関する厳しい条件が課せられます。たとえば防火地域では、「耐火構造」にしなければなりません。
準防火地域では、建物の延床面積に応じて講じるべき対策が異なります。
▸1,500m²超 ⇒ 耐火構造にする
▸500m²超、1,500m²以下 ⇒ 準耐火構造にする
▸500m²以下 ⇒ 一定の防火措置が求められる
参考:建築基準法第61条
参考:建築基準法施行令:第136条の2
参考:国土交通省「建築基準法制度概要集」p41
耐火構造や準耐火構造とは、どんな構造でしょうか?
耐火構造や準耐火構造は、火災が発生した際に避難できるように、一定時間は構造部材の「変形、溶融、破壊その他の損傷」が生じない性能を持つ構造です。
木造3階建ては、部位ごとに「30分から1時間」ほど燃え抜けない性能が求められます。
参考:建築基準法施行令第107条
参考:建築基準法施行令第107条の2
耐火構造や準耐火構造は、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)や開口部(窓、ドア)に厳しい規定が設けられています。
木造3階建てを検討している方は、まず建築予定地の防火指定を確認しましょう。そのうえで、耐火構造・準耐火構造の採用について建築会社と具体的に相談することが重要です。
なお、耐火構造や準耐火構造の木造住宅は、一般的な木造より火災保険料が大幅に安くなります。
木造3階建ては、鉄骨造に比べると構造の安定性を確保しにくい側面があります。
ただし、これは「木造が弱い」という意味ではなく、あくまで構造的な特性の違いによるものです。適切な設計と施工をおこなえば、木造でもじゅうぶんな安全性を確保できます。
木造(軸組工法)は、柱と梁を組み合わせ、「筋交い」や「構造用合板」と呼ばれる部材で補強した「耐力壁」で建物の安定性を保ちます。この耐力壁は、地震や強風に対抗する重要な壁です。
とくに3階建ての場合、各階にある耐力壁の量や配置バランスが建物の安定性に直結するため、間取りの自由度が制限されやすくなります。
一方、鉄骨造(ブレース工法)も柱と梁を組み、筋交いで補強します。ただし鉄骨は強度が高く、木造よりも筋交いの数を減らしたり、壁の配置の自由度を高めたりしやすいという特長があります。
》木造と鉄骨、どっちがいい?違いは?メリット・デメリットで比較
現在の木造3階建ては、建築確認申請の際に構造計算書の提出が必須です。これにより、建物の重量や地震時の揺れを考慮し、必要な耐力壁の量や配置を科学的に検証します。
木造3階建ては、鉄骨造と比べて構造の安定性の確保に工夫が必要ですが、適切な設計と最新の技術を組み合わせることで鉄骨造に劣らない安全性を実現することが可能です。
どちらの構造を選ぶにしても「耐震性」や「間取りの希望」を明確にし、その両方を満たせる設計ができるか、建築会社としっかり相談することが重要です。

都市部で木造3階建てが選ばれるのは、狭い土地を有効活用できるだけでなく、デメリットを補って余りあるメリットがあるからです。
ここからは、鉄骨造と比べたときの木造3階建てならではの魅力をご紹介します。
▸建築費や税金などのコストを抑えられる
▸地震のダメージが少なくなる傾向がある
▸地盤への負担が少ない
順番に、詳しく解説します。
木造3階建ては、同じ3階建てでも鉄骨造に比べて建築費や固定資産税などのコストを抑えられる傾向があります。
建築時だけでなく、長期的に見ても「経済的なメリット」を感じやすい住宅です。
木造住宅は、鉄骨造に比べて材料費や施工コストを低く抑えられます。施工のスピードや人件費の面でもコストダウンが期待できます。
鉄骨は工場での加工や現場への運搬にコストがかかるうえ、建物自体が重くなるため、地盤改良工事が必要になる可能性が高まります。
新築住宅の固定資産税は、建築費が高いほど評価額も高くなり、税額が上がる傾向があります。なぜなら、固定資産税は対象となる資産の時価をもとに税額を計算するからです。
ちなみに「2024年度 建築物着工統計」によると、建築費(建築主:個人)の平米単価は以下のようになっています。
▸木造:24.79万円/m²
▸鉄骨造:32.99万円/m²
平均値では、1.3倍程度「鉄骨」のほうが高くなる計算です。
ただし、これは同水準の住宅を比較した場合です。鉄骨であっても小規模・低額な物件は固定資産税も低くなります。
一方、木造であっても、大規模・高額な物件はそれだげ固定資産税も高くなりやすい点は注意が必要です。
木材は鉄骨に比べて熱伝導率が低く、断熱性に優れています。そのため、冷暖房効率の向上に貢献し、光熱費を抑えやすくなります。
ただし、シロアリ対策など、木造特有のメンテナンス費用も考慮する必要があります。
コスト面で住宅を選ぶ場合は、初期費用だけでなく、固定資産税や光熱費、メンテナンス費用を含めた「ライフサイクルコスト」で比較するのがおすすめです。
地震の揺れによって建物に加わる力は、建物の重さに比例して大きくなります (ma=F:質量×加速度=力)。
木材は鉄骨に比べて軽いため、木造は鉄骨造より建物全体の重量が軽くなる傾向があります。建物が軽いと、地震の揺れで加わる力が小さくなり、結果として受けるダメージも少なくなります。
一方、鉄骨造は建物全体の重量が重く、地震の揺れで建物に加わる力が大きくなります。木造住宅の軽さは、耐震面では大きな利点となります。
木造3階建ては鉄骨造に比べて建物自体が軽く、その分、地盤への負担が小さくなります。その結果、地盤改良工事が不要になったり、必要であっても小規模で済んだりするケースが増えます。
一方で鉄骨造は、地盤が比較的柔らかいエリアでは、大規模な改良工事が必要になるケースが少なくありません。そのため、費用と工期が膨らみがちです。
木造の「軽さ」という特性は、耐震性においても有利に働く側面があります。制震構造を採用したり、耐震等級3を取得したりすることで、さらに高い安全性を確保できます。
》耐震等級3なら倒壊しない?これからの耐震ニューノーマルを考えよう

木造3階建ては、設計や施工の工夫次第で快適かつ安全な住まいを実現できます。一方、構造や素材の特性上、気を付けたいポイントもあります。
その主なものが「腐朽・蟻害対策」と「建築会社選び」です。
木造住宅は主要構造材に木材を使用しているため、鉄骨造に比べて湿気による腐朽やシロアリによる食害のリスクが高くなります。
これらの被害は耐久性や耐震性を著しく低下させる恐れがあるため、建築時から予防対策をおこない、定期的なメンテナンスを欠かさないことが重要です。
鉄骨造も木材を使用しているため、シロアリに注意しなくていいわけではありませんが、木造はより配慮が必要とお考えください。
建築時には、以下の対策が防蟻・防腐に有効です。
▸防蟻・防腐処理
▸通気性の確保
▸断熱材の選択
まず、シロアリや腐朽菌の被害を受けやすい土台や1階床下部分の木材に、防腐・防蟻剤をしっかりと塗布するとよいでしょう。
さらに、床下に湿気がこもらないようにし、必要に応じて床下換気扇を設置することで通気性を確保します。
断熱材の選択も重要です。断熱材の中には、シロアリの食害に遭いにくいものやシロアリを死滅させるものがあります。
例をあげてみましょう。
▸無機質のグラスウールやロックウール
▸ホウ酸配合のセルローズファイバー
防蟻を徹底したい場合は、上述のような素材を採用すると安心です。ただし、断熱材の選択は、断熱性能や耐水性、コストも考慮する必要があります。
新築時に施された防蟻処理は、一般的に5年ほどで効果が切れてしまいます。そのため、定期的に専門業者による点検を受け、必要に応じて再処理をおこなうことが大切です。
あわせて、結露の発生を防いだり、水回りの水漏れがないか日常的に確認したりすることで、木材の劣化を最小限に抑えることができます。
木造であっても、適切な対策を講じ定期的なメンテナンスを怠らなければ、長期間にわたり安心して住み続けることが可能です。
木造3階建てを建てる際には、信頼できる建築会社を選ぶことが何より重要です。木造3階建ては、2階建てに比べて構造が複雑で、より高い設計・施工技術と法規の理解が求められます。
建築会社に求められる能力の例をあげておきます。
▸構造計算:計算を正確におこない、適切な構造設計ができる技術力
▸耐震性:3階建ての構造的な知識と、豊富な建築経験
▸高さ制限:地域の高さ規制を理解し、施主の希望する家を実現する設計力
▸耐火構造:耐火建築物または準耐火建築物に合致させるノウハウ
これらはいずれも専門性が高く、施主が自分で判断・実行するのが難しい分野です。経験不足の業者に依頼すると、設計の自由度や安全性に影響が出るリスクもあります。
後悔のない家づくりを実現するためには、木造3階建ての施工実績が豊富で、最新の法改正や技術にも対応できる知識を持った建築会社を選びましょう。
》3階建て住宅のメリット・デメリットは?高さ制限等の注意点も紹介
木造3階建て住宅のメリットとデメリットをご紹介しました。大切なのは、このような両面を理解し、自分たちの予算やライフスタイル、立地条件に照らし合わせて計画を進めることです。
しっかりと情報を集め、木造3階建ての実績が豊富な建築会社と相談しながら家づくりを進めれば、安心・快適で長く愛せる「木造3階建て」を実現できるでしょう。
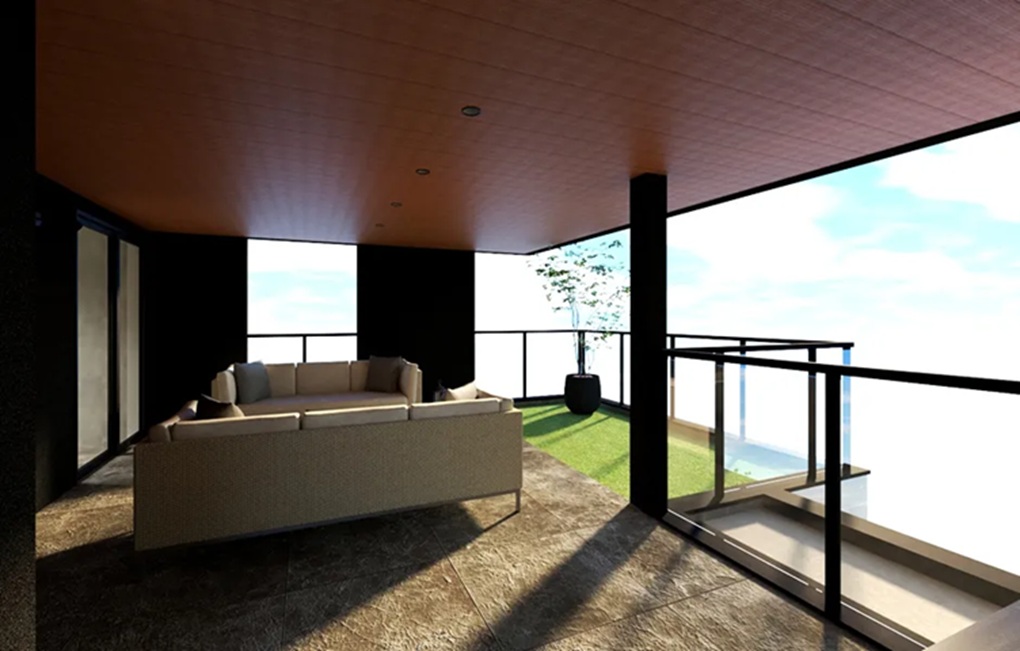
創建ホームは、広島県で7,000棟を超える注文住宅の実績があり、木造建築に精通しています。耐火地域における3階建て住宅も数多く手がけていますので、お気軽にご相談ください。
創建ホーム「空とつながる 3階建てスカイバルコニーの家」はこちら 》









